| 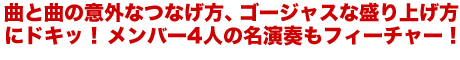
ビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーティンとその息子ジャイルズが、ビートルズのニューアルバムを作ったと騒がれた『LOVE』。もともとは、ビートルズの歌をモチーフにした同名のショーが原点となっているのだが、ショーのサントラではなく、正式にビートルズの新作として作り上げられたものだ。そのため、発売前からファンの間で、オリジナルの冒とくになるのではないかという懸念があった。これが『ネイキッド』ほど話題にならなかったのは、『ネイキッド』はビートルズのオリジナルの原型をほとんどとどめていたのに対し、『LOVE』はジョージ・マーティンとその息子によるビートルズの楽曲を使った大編集プロジェクトだったからであろう。そのため、このアルバムの評価の対象は、マーティン親子に向けるべきである。ビートルズは神聖なものなので、これをビートルズの新作としてオリジナルラインナップに入れるわけにはいかない。あくまでも、ジョージ・マーティンの新作と見たい。それがビートルマニアに対しての礼儀ではないか。
アルバムのテーマは、『アビー・ロード』のB面を、サイケデリックにアレンジしたようなものと思ってもらうとわかりやすいかもしれない。平たく言えばビートルズのコラージュ作品である。使われている音の99%はビートルズのマスターテープから引っ張り出されたされたものである。そう聞くと『アンソロジー』を想像される方もいるかもしれない。しかしフタを開けてみると中身は全然違っていた。『アンソロジー』はあらゆる素材を集めた資料的な音源であって<作品>ではなかったが、『LOVE』はきちんとした1本の<作品>に仕上げられているのである。ビートルズの有名なフレーズが、万華鏡のように次から次へと反響し、音が立体的に膨らんでいく。あえてCDと5.1chのDVDオーディオをセットにしたのもよくわかる。「ビコーズ」と「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」を聴いても、音質、音の厚み、立体感などは明らかに『アンソロジー』のそれよりもグレードアップしている。『アンソロジー』の雑な音を知るものとしては、この丁寧に作り込まれた音のコラージュ、鮮やかなサウンドには驚くばかりであろう。ビートルズの作品として後世に残ることはなきにしも、いわゆるリミックス系統の作品としては、歴史的な1枚になり得る。こういう売り方を今後助長しないかと心配にもなってくるほど豪快な1枚である。
正直、ビートルズのオリジナル曲をいじくられるのはファンとして許せないものがあったが、僕は御大マーティンを見くびっていた。唯ひとり聖域に入れる男。これはどこから聴いてもビートルズそのものだ。絶対に紛い物のアルバムになると思っていたが、ズカンとやられた気分である。オリジナルの良さはほとんど損なわれていない。それどころか、「ヘイ・ジュード」のベースラインが強調されるなど、新しい発見もある。4人のみずみずしい歌声はもちろんだが、注目して欲しいのは4人メンバー各人の演奏の好プレーのパートをフィーチャーしているところだ。まずトラック2「ジ・エンド」でのリンゴのドラムソロから始まるところにゾクゾクさせられる。そこから自然に「ゲット・バック」へと移り変わっていくが、このつながりがあまりにも絶妙なので、僕はこの瞬間から引き込まれて、がぜん熱くなった。
このアルバムは、ビートルズの曲と曲が、なんとも意表をついた形でドッキングしている。曲と曲がつながる瞬間の盛り上げ方が実にゴージャスで、ファンならば思わずハッとしてしまうことだろう。選択されているナンバーは、スタジオ録音に徹していた頃の後期の曲が多いが、この時期の方が音を分解して再構築しやすかったからだろう。「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」に「ペニー・レイン」のフレーズを入れるなど、多少狙いすぎて失敗しているところもあり、他にも「ブラックバード」から唐突に「イエスタデイ」に移ったり、「レヴォリューション」から「バック・イン・ザ・USSR」につなぐところなど、かなりぶつ切りで強引な印象もあるが、部分部分をとって聴くと、なかなか興味深いところが多い。「ヒア・カムズ・ザ・サン」に「ジ・インナー・ライト」のインド楽器の伴奏が不思議とマッチしているし、まさか「ピッギーズ」と「ハロー・グッバイ」がこんなにも相性が良かったなんて誰が気づいただろうか。唯一初期の曲では「抱きしめたい」が引用されているが、これは曲全体を丸ごとライブ風に演出しており、ビートルズをおおいに讃えている。
曲と曲をフェードインで直列につなげた曲よりも、2曲を思い切って並列に再生した曲の方が味がある。「ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー」と「トゥモロー・ネヴァー・ノウズ」の見事なシンクロには、御大マーティンのプロデュース力の神秘を見た。僕は特にここから「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ」に移っていくパートが気に入った。5.1chで聴くと、音のふくらみ方がマジカルでファンタスティック。このアルバムでは出色の出来栄えだろう。
ライナーに<宝石箱>と書かれてあったが、まさにその通りであろう。4人のメンバー全員の良さを満遍なくちりばめた、ビートルズファンにとっては大興奮の1時間半。友達にも聴かせたくてうずうずしてくるが、これを聴くためには、ビートルズの全アルバムを、アンソロジーも含めてすべて聴いていることが大前提だ。これからビートルズを聴こうと思っている人には聴かせたくないのが正直なところ。ビートルズの曲を全部空で歌えるくらいになってから到達できる領域だと思う。ビートルズを愛してなくちゃ始まらない。最初の曲が「ビコーズ」で最後の曲が「愛こそはすべて」というのは「なぜなら愛こそはすべてだから」というメッセージとしてとれるが、僕にとってこのアルバムタイトルは、ビートルズに対する愛としか思えないくらいである。
ジョージ・マーティンのビートルズからみの作品としては、以前『イン・マイ・ライフ』というアルバムがあった。ジェフ・ベックやセリーヌ・ディオンなどが参加していたカバー集であるが、今ひとつ物足りない印象があった。しかし『LOVE』は『イン・マイ・ライフ』とは比べられないほどの熱気に満ちている。それはなぜかというと、演奏している人がビートルズに他ならないからである。やはりビートルズは、ビートルズでなければならないのだ。
「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」の伴奏のみ、ジョージ・マーティンがスコアを書き下ろしている。「イエスタデイ」でストリングスを書き足したマーティンならではの傑作で、この曲が本作品最大の目玉となっているのは間違いない。ジョージの演奏は、『アンソロジー』でも聴かれたアコースティックバージョンが使われているが、『アンソロジー』よりも音がくっきりしていて、ジョージの美しい歌声にただただ感動するばかりである。このアルバムにはジョージの曲が5曲も使われているが、どの曲も繊細で瑞々しく、やはりジョージにはジョン、ポールと同等の賛辞を贈ってしかるべきだと思う。
「ヘイ・ジュード」では良い気分になっているところで出し抜けに「サージェント・ペパー」に曲が変わってしまうので、もうちょっと余韻に浸っていたかったという気もする。前半は引用が長かったり短かったり、後半は「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」で幕締めかと思いきや、その後もラストソング向けの曲が2・3曲続くため、アルバムのトータル性としては微妙な出来だ。もう少し時間をかけて、1時間半まったく一連の流れを殺がないトータルアルバムにしていれば、もっと評価は高くなったかもしれない。このまとめ方では否定派による辛口のツッコミは避けられないが、僕自身は本作はイルミネーションショーを見る感覚で存分に楽しませてもらった。こうして聴くとあらためてビートルズはロックのあらゆる形体を生み出した変革者だと再確認させられる。これには謎も仕掛けられているようなので、後年になって化ける可能性も大きい。しょせんはベストアルバム扱いなので、オリジナルアルバムほどの愛着はどうしてもわかないが、面白い作品なので、一度くらいはこのひとときを体感すべし。
|