| 「完璧」という形容が通用するバンドは、ピンク・フロイドをおいて他にはない。一枚一枚が捨て曲ゼロの完璧なアルバム。アバンギャルドで難解な内容にして、ファーストから「雲の影」までのアルバムはすべてチャートのトップ10圏内に入り、それ以降から現在までの全アルバムがチャートのトップ5圏内。「狂気」に関しては741週連続チャート・インするというギネス・ブック公認の驚異的記録を誇る。彼らのオリジナル・アルバムのすべては全曲が自作ナンバー、トータル・コンセプトで作られている。まったく新しい音響効果が駆使されたエポックメーキングなスタジオ盤と、それに劣らぬ幻想的なライヴ・パフォーマンス。ありとあらゆるところで非の打ち所がない怪物バンドである。
ピンク・フロイドは、ロンドンの建築学校に通うロジャー・ウォーターズ(1944−)、ニック・メイスン(1945−)、リチャード・ライト(1945−)の3人の同級生が、音楽について論争しているうちに「バンドをやろう」と言い出したのがすべての始まりである。メンバーは皆インテリで、裕福な家庭に育っていたので、楽器は親から買ってもらったのだという。まもなく、美術学校のシド・バレット(1946−2006)をヴォーカルに加え、65年にサイケデリック・ロック・グループ、ピンク・フロイドを結成した。66年10月には早速ライブにライト・ショーを導入。この経験がやがて巨大化していくピンク・フロイドの起爆剤となるのだ。
67年3月。ピンク・フロイドは待望のファースト・シングル「アーノルド・レイン」を引っさげてプロ・デビューを飾った。これがチャートの20位に入り、好調のスタートを切る。8月にはファースト・アルバム「夜明けの口笛吹き」を発表。名曲「天の支配」を含む同作は、チャートの6位に入る成功をおさめた。シドのポップ・アート的な感覚と3人の構築的な演奏のアンサンブルが特徴的だったが、実質的なリーダーであったシド・バレットは精神を病み、この頃から廃人同様になっていた。ライヴ中にふと歌うのをやめて、うつろな目をしたまま、呆然と立ちつくしたこともあり、脱退を余儀なくされた。シドの後任としてデヴィッド・ギルモア(1947−)が加入するが、シドの生き様はその後のピンク・フロイドの精神的存在として、永遠に生きていくことになる。メンバーは、サウンドの雰囲気とは裏腹に、決してドラッグには手を出さなかったと言っていたが、これも彼らがシドを見てきたためか、精神病に打ち克つ意志があったからだろう。ちなみにシドのそのスタイルは後にグラム・ロックのお手本となった。
シド脱退直後のピンク・フロイドは、勢いづき、最もバンドとしてのバランスがとれていた時期である。各自が作曲家として楽曲を提供し、各自が演奏で自己主張をしていた。その中で生まれた「神秘」「ユージン、斧に気をつけろ」「太陽賛歌」は、ピンク・フロイドの定番といえる名曲である。これらが収録された2枚組の大作「ウマグマ」は、楽曲・演奏面共に最も充実していた作品で、ピンク・フロイドというバンドの音楽性、ライヴ・パフォーマンスの奇抜さ、スタジオ・レコーディングの革新性を確認できる名盤である。ところがメンバーはこの頃の演奏をよしとしていない。まだこの当時は彼らにとって実験段間の発展途上状態だったという。その後、ウォーターズは音楽にコンセプト性とショーの感覚を持たせようと作風を変え、ギルモアはギター・サウンドを推し進め演奏を中心とした音楽志向に目覚めていく。
世界の人気を確立したのは24分の組曲「エコーズ」が決定的だった。緻密な構成力と、音響を意識した感性溢れる演奏。ソナー音のような最初のピアノのたった1音の魔力。1音だけなのに、その音の響きが聴く者の魂を揺さぶってやまない。テクニックではなくセンス。それがピンク・フロイドだ。そのスタイルをよりポピュラーでつかみやすいものにした「狂気」は20世紀音楽史における最高の文化遺産といえよう。
以前から作詞を担当し、アルバムの指導者であり演出者であったウォーターズは、「アニマルズ」あたりから、ピンク・フロイドそのものを呑み込んでいった。いつしかメンバーの連帯感は薄れ、ウォーターズはリチャード・ライトを無能として解雇する。ウォーターズのソロ作品をピンク・フロイドの連中に演奏させたともいうべき「ファイナル・カット」を発表後、ウォーターズはバンドの限界説を掲げ、83年にバンドを解散させるのだった。
ところが、ギルモアは「ピンク・フロイドはウォーターズだけのバンドではなくメンバー全員のバンドだ」として、バンドをこれからも継続していくことを決意。メイスンと2人でピンク・フロイドの新たなる活動をスタートさせる。ウォーターズはこれに腹を立て、ギルモアを相手取り訴えるが、ギルモアはウォーターズのその身勝手な態度に猛反発。二人は顔も見たくない犬猿の仲となるが、結局はギルモアがその後の売上の一部をウォーターズに支払うことで解決するのだった。87年には新生ピンク・フロイドにより4年ぶりの新作「鬱」をリリースし、絶賛された。ギルモア中心のフロイドはウォーターズ中心のフロイドとはまた違ったメロディアスな美しさがあった。その後リチャード・ライトが正式メンバーとして復帰。レーザー・ショウを駆使した大がかりなライブ・パフォーマンスはロック史に燦然と輝く巨大な伝説を刻み込んだ。
→ピンク・フロイド・アルバム・ランキング
→ピンク・フロイド・ソング・ランキング
→ピンク・フロイド ワールド・ツアー1994
Amazonで「ピンク・フロイド」を検索
ベストフィルム「神秘」(YouTube)

<1965年〜1967年>ピンク・フロイドの活動は4つの時代に大別することができる。まずバンド結成時からレコード・デビューまでの第1時代がシド・バレットの時代。この頃の活動については、ロジャーも「シド以外は誰でも良かった」と語っているくらいで、実質的にシド・バレットがすべての指揮権を握っていた。この時代には1枚のアルバムしか発表してないが、この1枚がなければピンク・フロイドもなかったので、シド・バレットこそバンドの生みの親といえる。サウンド的にはシドのポップ・センスが光る。かきならすギターのサウンドがサイケデリックな雰囲気を醸し出す。シドは良く言えば無邪気なアーチストだった。そこに他の3人が建築的に音を重ねていった。バンド・メンバーの中で生まれつきの天才肌はシドだけだった。
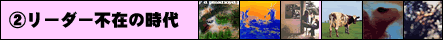
<1968年〜1973年>次は「神秘」から「狂気」に至るまでのリーダー不在の時代。早くもシドが脱退し、リーダーを失ったピンク・フロイドは、民主主義的なスタンスで、実験的な音楽を次々と作り出していった。この頃の興味深い点は、それぞれのメンバーが平等の立場に立っていたことだ。「ウマグマ」では4人それぞれが作曲して曲を出し合っている。ライブ活動も積極的だったが、この頃はギター、ベース、ドラム、オルガンだけで、いかに優れた音楽を作り上げるかに定評があった。ベースの弦を擦るなどして、それまでのロック・バンドには見られない音響を意識した立体的な音作りは世間を圧倒した。まさに「エコーズ」は4ピース音楽の最高傑作といえる。そしてその実験的なスタイルが初めてわかりやすいスタイルで結実したのが「狂気」だった。なお、この時代のリチャード・ライトの活躍ぶりは目覚ましいもので、バンドの中でも最も目立っていたといっても過言ではない。僕自身はこの頃のピンク・フロイドが一番面白かったと思う。

<1973年〜1983年>続いて「狂気」あたりから「ファイナル・カット」までのロジャー・ウォーターズ時代。この頃がバンドの評価が最も高かった時代だ。ロジャーは「狂気」の全ての歌詞を担当していた。そのころからしだいにロジャーが頭角をあらわし、バンドのリーダー的存在になっていく。それまでは4人だけの演奏にこだわり続けていた彼らが「狂気」以降、シンセサイザーやサックスなどあらゆる楽器を導入し、音をさらに広げていく。「狂気」のあと、しばらく途方に暮れていた彼らは、シドを回想し「炎」を完成させる。これ以降はほとんどの曲をロジャーが中心になって作曲することになる。それまではデヴィッド・ギルモアとリチャード・ライト寄りだったヴォーカル担当者もこれ以降ロジャー寄りに傾く。あれほど音響にこだわり続けていた彼らが、今度はコンセプト志向になり、ロジャーなりの哲学観が表れるようになる。またロジャーの意志でライブも巨大なショーとして演出するようになる。2枚組としては世界一売れた「ザ・ウォール」はまさにショーとして披露するために作られたような作品で、ここでバンドは頂点を極める。

<1987年〜1995年>最後は「鬱」から「PULSE」までのデヴィッド・ギルモア世代。頂点を極めたことでロジャー自身の手によって活動停止になったピンク・フロイドだったが、今度はギルモアが中心となって動き始める。ただしロジャー抜きで。ギルモアは以前から様々なミュージシャンとセッションを繰り返してきた社交家だったが、新生ピンク・フロイドではその人脈を生かして外部から様々のミュージシャンを参加させての録音となった。コンセプト志向のロジャーとは異なり、前々から音にこだわり続けていたギルモアはメロディ主体のサウンドを打ち出すが、ロジャーのショー志向はギルモアも受け継ぎ、ピンク・フロイドの名に恥じないよう大がかりなライブ・パフォーマンスでも有名になる。ただし過去の栄光への回顧のような感じも否めなかった。
それから10年ものブランクを置いた後、2005年ライブ8で、ロジャーが久しぶりにバンドに復帰、4人全員揃ってのライブが25年ぶりに実現し、ファンを泣かせたのは記憶に新しい。
|